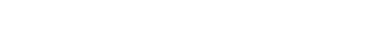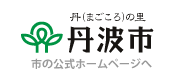今日の一歩は明日を変える6月
6月終了
 |
地区懇談会
 |
|
|
7月28日 金曜日 PTA主催で地区懇談会を実施しました。各自治会長様を始め、民生委員様、その他、各地区でご出席いただきました。鴨庄地区では、統合した昨年度からは、全自治会が集まり、鴨庄コミセンで実施しています。ラジオ体操のこと、地区内のパトロールのこと、鴨庄サマースクールinナイトのことなど、話し合われました。子どもの見守り・お世話をしてもらうだけでなく、保護者の世代も、高齢者の見守りを兼ねてパトロールに加わるなど、よい関係を築かれています。 |
吉見金管バンド
|
6月28日 金曜日 今は、7月28日(日)市島川裾祭りで発表する曲を練習しています。5年生が発表するのは初めてになります。暑い日もありますが、昼休みの30分間、総合的な学習の時間を練習にあて、コツコツと積み上げていきます。 日々のロングトーンや基礎練習は、金管楽器奏者にとって絶対にこなさなければならない日課です。実は、プロの人も、楽器を始めたばかりの吉見小5年生も、共通してこれに取り組んでいます。このような所作は、今後の児童たちの人生に、よい影響、よい教訓になると確信します。 |
|
 |
 |
クラブ活動5回目
 |
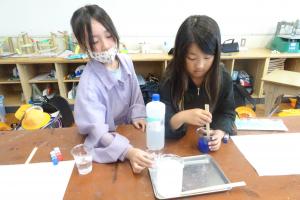 |
| チョコパイづくり | スライムづくり |
 |
 |
| イラストクラブ | スポーツクラブ |
 |
|
| パソコンクラブでは、流行歌を耳コピして音源をつくりました。 | |
食育指導
| 年間を通して、どの学年にも、栄養教諭による食育指導をしています。今回、4年生では、給食前の15分間を使い、朝食の大切さを学びました。いずれ、児童も一人で暮らしたり、自分が家族の食事を作る大人になっていきます。このような指導は、生涯にわたって役に立っていきます。7月1日から7月7日までは吉見小健康チャレンジ週間です。朝食のチェックもあります。 | |
 |
 |
金管の起こり
 |
|
|
6月21日 金曜日 吉見金管バンド創立時の教職員が、金管の起こりについて、継承に来てくれました。毎年、不思議に思うのですが、このお話を子どもたちはとても興味を持って、メモを取りながら食い入るように聞くのです。自分たちのオリジナリティな活動の事だからでしょうか。 アイデンティティの確立は吉見小でしかできない体験、学習、吉見小でしか会えない友だち、先生、地域の環境や人々によって作られていきます。市島町や丹波市の、自然などの環境や景色も、大きな要因になるでしょう。「他者の中で自分らしくいられる」ために、自分の中(心身)にオリジナルの学習や出来事をたくさん蓄積してほしいと思います。 |
川探検3年
|
6月14日と19日、市島大橋と鴨庄川の2カ所に行って川探検をしました。両地区からゲストティーチャーを呼び、2か所共に参加していただきました。校区が広がり、2つの場所では、住む生き物や川の形が違っていることを、子どもたちは興味を持って受け止めました。 昨年度の学校運営協議会の中で「環境問題=SDGS」の視点を入れていくことのご意見をいただきました。3年生では理科や社会科の学習が、環境問題と密接に絡み合っています。これまでの人工構造物ベースのインフラは、エネルギーや人材の集中的な投入を前提に作られていますが、人口が減少し、経済も縮小する今、その全ては維持できません。それぞれの地域で、自然の営力にあわせた土地利用や生活スタイルのあり方を考えていくフェーズにさしかかっています。 |
|
 |
 |
| 市島大橋下での観察 | |
 |
 |
| オドノ橋付近、鴨庄川での観察 | |
第2回学校運営協議会
|
6月18日 火曜日 第2回学校運営協議会では(1)学校の様子(2)授業参観(3)意見聴取(4)熟議の計画(5)統合の進捗状況について話し合いました。 【意見聴取より抜粋】■統合を期に、学校がどんどん変わっているのが分かる。子どもも、先生も、変わる、変われるというエネルギーや力がすごい。段階的な統合が控えており、先生方にも苦労を掛けるがよろしくおねがいしたい。/■オープンスクールで1年と6年が隣同士で驚いたと同時に、とてもよい考えだと思う。6年生の下級生のお世話をする意識、1年生の6年生から自然に身に付ける事柄など多くの利点が考えられる。/■こども園との連携が安心感を生んでいる。1年生も順調に育っている。/■毎日登校見守りをしている。4月に表情が硬かった1年生も5月には緊張が解けた。笑顔が全体的に多い。欠席者も少ない。/■1年生でも黒板に紙が貼られるとスッと視線が集まる。日頃の指導が伺われる。/■各先生がとても上手に指導されている。個々の子どもに丁寧に接している。/■あいさつをする子が多い。近年は子どもが少ないが異学年交流をたくさんされているので心配はしていない。/■サマースクールは昔の「てんじんこう」のような楽しいことをしてやろうと思った。子どもが少ない自治会では行事をしないとのこと、さみしいと思い役員で話し合った。星観察や肝試しなど計画しているので保護者にも関わってほしい。/■近所に吉見地区からも来ていて行動範囲が広がっていることが伺われる。地域でどのように子どもを育てていくかが課題。子どもが参加したいと思うような子どもを主役にするイベントをしていきたい。 (2)熟議について 日 時 8月28日 水曜日 19時00分から20時00分 場 所 ライフピアいちじま 研修室234 題 目 「一日一笑」~笑う門には福来る~ 参加者 吉見小校区住民・教職員など(*進行役は委員が行います) |
鴨庄太鼓
 |
|
| 6月18日 火曜日 旧鴨庄小学校からの継続で、太鼓創立の時の教職員がゲストティーチャーで来てくれました。現5年生から「口唱和」や「叩き方」などを教わった3年生ですが、更に技術を磨くために、2回の予定でレクチャーを受けます。正味30分程の指導で、フォーム、強弱、叩く場所、撥の位置などが、見違えるように良くなりました。また、準備や片付けは自分の分だけでなく、全員で取り組むことを心掛けるように教えていただきました。次回までに直そうと、4年生は意気込んでいるのが伝わりました。 | |
 |
 |
| 腕・バチ | つま先の向き・腰 |
 |
 |
| 腕から撥へ一直線 | 叩きながら確かめ |
4年親子活動
| 6月16日 日曜日 4年生のPTA親子活動が実施されました。校区内のパン工房でパン作りをされ、交流を深められました。4年生は、令和8年市島小学校の開校時に6年生になる学年です。保護者の方々にも、三輪小学校との統合に向け、保護者間のつながりをお願いしたいところです。 |
能楽鑑賞会
| 6月13日 木曜日 丹波能楽振興会のみなさまによる、芸術鑑賞会が開かれ、6年生がライフピアいちじま大ホールに出かけました。校区内の鴨庄地区にある神池・吉見伝左衛門…などを題材にされた新作も演じられました。そのせいか、テレビニュースでは、吉見小の児童がインタビューを受けました。 |
ゲストティーチャー水泳
 |
|
|
県のプロジェクト「体力アップサポータ―派遣事業」で水泳の専門指導を受けました。 吉見小では考える体育(自律)を展開できるよう工夫しています。いつも「できるようになるにはどうしたらよいか」という視点を持つように工夫しています。低学年では課題解決の運動の仕方を知って、友だちのよい動きを見つけるようにしたり、高学年では課題解決に向けて運動の仕方を選んだり工夫したりできる授業展開をしています。今日の水泳はまさにそのような授業になりました。 |
校歌歌詞・校章
|
【統合準備委員より】昨夜開催された統合準備委員会にて、令和8年4月開校予定の市島小学校、校歌歌詞の原案が決定されました。 全国より公募された91作品は、段階を追って6作品に絞られました。その後、1作品ずつ朗読・意見交換・オブザーバー2名の講評を繰り返し、更に3作品に絞るなど熟考された後、決定に至りました。 決定された作品は、市島の豊かな自然を思わせる詞に、育ってほしい児童姿や心情面がうたわれ、最後には、児童が学校で一番大切にしている「友だち」が使われ「市島小学校」に繋いで締めくくられます。 作曲は、プロの作曲家に依頼することが決定済みです。作曲の過程で、多少の文字の変更があるかもしれません。本年度末には完成を予定しています。以下、歌詞(原案)を掲載します。今後共、統合準備に係り、ご理解・ご協力いただきますようお願いいたします。(吉見小選出委員より) 1丹波のやまなみ 陽に映えて みどり輝く この町に 明るい声が こだまする 今日も明日も 元気よく ともに生きよう わたしたち みんな友だち 市島小学校 2朝霧晴れて 光さす 実り豊かな この里に 大きな夢を えがきゆく まっすぐ伸びる なかまたち ずっと友だち 市島小学校 作詞者の言葉:故郷の市島の自然、好きな風景を歌詞に入れました。市島小学校が、ずっと未来に続いていきますようにという思いで書きました。以上 |
 |
| 6日には、校章デザインの原案が決定しています。吉見の「吉」の文字 鴨庄の「鴨の絵」 三輪の「三つの輪」 統合する小学校の特徴すべてをアレンジしたデザインが、全国より公募された231作品の中より選ばれました。今後、色や図案の微調整がされ採用になります。 |
体育 1年
 |
|
| 6月12日 水曜日 1年生の体育では、指導者が「どうしたら、はやく歩けますか」と問いかけました。「手を早く動かす」「手のひらをこんな形にする」「足を速く動かす」などと答えたあと、たいこの合図で向こう側まで競争します。次第に、蹴伸びで泳ぐ子も出てきました。自然な形で水に親しみ、泳ぎに必要なことを覚えていきます。水の中で屈伸運動をしたり、飛び跳ねる運動をして、必然的に肩まで浸かり、顔に水を浴び、楽しさのあまり苦手意識も吹っ飛んでいました。 | |
 |
 |
オープンスクール
 |
|
| 1年 | |
|
6月11日 火曜日 8時15分から15時45分までの学校生活を、地域・ご家庭に公開しました。多数、来校いただき、ありがとうございました。児童も教員も普段通りの姿を見せていました。しかし、人の出入りがあり、集中力を切らさないように、児童や教員は、普段よりエネルギーを使ったと思います。一日を断続的に参観された方が「子どもたちが、このスケジュール(校時)をよくこなしていますね、びっくりします。」と感想を言われました。「これが、毎日の学校生活です。」と返答しながら、労働に匹敵するくらいのエネルギーだと再認識させられました。「だからこそ、家庭では栄養や睡眠を十分にとってやってくださいね」とお応えしました。 |
|
 |
 |
| 2年 | 3年 |
 |
 |
| 4年 | 5年 |
 |
 |
| 6年 | 1年 |
親子活動 1・5年
|
6月8・9日 土曜日・日曜日 1年・5年の親子活動が実施されました。1年生は、親子で紙ヒコーキをつくり、競い合われました。5年生は、ドッチビーをされました。お家の方も、久しぶりに、童心・スリルを味わわれ、楽しい会になりました。互いの理解を深める有意義な行事になりました。 |
|
 |
 |
読み聞かせ
|
6月7日 金曜日 毎月、第一金曜日の朝学習は、地域の方による読み聞かせです。ボランティアグループを「絆」と名付けておられます。今回、お家の方より参加したいというお声をいただき、見学に来られました。来月から加わっていただくことになりました。大歓迎です。 |
||
 |
 |
 |
 |
 |
 |
ごみの行方 4年
|
6月3日 家や学校から出ているごみの種類や量について調べ、「ごみは種類によって集める曜日が違うのはなぜだろう」「私たちが出している大量のごみは、どこに行くのだろう」などという問いをもち、見学に行きました。 |
|
 |
 |
 |
 |
音読
 |
|
|
6月3日 月曜日 3年生は、国語の授業で音読の発表をしました。場面やとうじょう人物の様子を想像して読みます。3年生では音読の記号をつくり、「間をとる」「はやく」「ゆっくり」「つよく」「よわく」「たかく」「ひくく」などの工夫を凝らして音読に取り組んでいます。 【お家の方へ】本年度、1年から6年まで毎日「音読」を、お家の方に聞いてもらうことを、課題にしています。毎日サインをいただき、ありがとうございます。読み終わったら、すぐにフィードバックすることが大切です。それにより、脳はさらに活性化するためです。これは、脳科学で「即時フィードバック」と呼ばれる効果となります。 フィードバックは、ポジティブなものであることが大原則です。まずは、前向きな感想を伝えてください。「上手だね」という言い方しか浮かばない…という方もいらっしゃる方もいるかもしれませんが、褒め方のバリエーションはたくさんあるものです。「やさしい声で読めたね」「大きな声で元気があったね」「ていねいに読めていたね」「スラスラ読めてすごい!」「聞き取りやすいスピードだったよ」など、何が良かったかも含めて伝えてあげてください。子どもが自分の音読を振り返ることができるよう、「ここのセリフをゆっくり読んだのはなぜ?」など、子どもの工夫を問いかけると効果的です。効果を最大化するためには保護者の関わりは欠かせないものです。よろしくお願いいたします。 |
|
 |
 |
市島地域自然学校 5年
 |
|
|
5月30日から5日間 自然学校は平成3年に兵庫県全小学校で実施されるようになってから約30年続いています。保護者の半数ほどは、ご自身も体験されたのではないでしょうか。 家庭を離れて、4泊5日の、非日常的な生活の中で、他校の児童と集団生活を送る経験は貴重だと言えます。また、メディア・ICT機器から遮断された生活も、児童にとって貴重な体験になったと思います。5日間は、あえて、家庭への情報提供をせず、離れて暮らしていただきました。様子はお子さんから聞いてください。 今年は、自分で判断して動ける「しおり」を意識して作ってくれたので、児童の言動には、大人を頼らず自分達で考える場面が多く見られました。本校の5年生にも予想をはるかに超えた成長が見られました。 |
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
おもしろ情報館
| 6月 学校運営協議会、保護者選出の方々による掲示板「おもしろ情報館」は、学校で児童が最も頻繁に通る廊下に位置しています。統合後、お互いの地域を知り合うことを一番の目標に、季節や学校の目標にも沿った内容での情報提供をしてくださいます。子どもたちの興味をそそる内容を考えていただきありがとうございます。 | |
 |